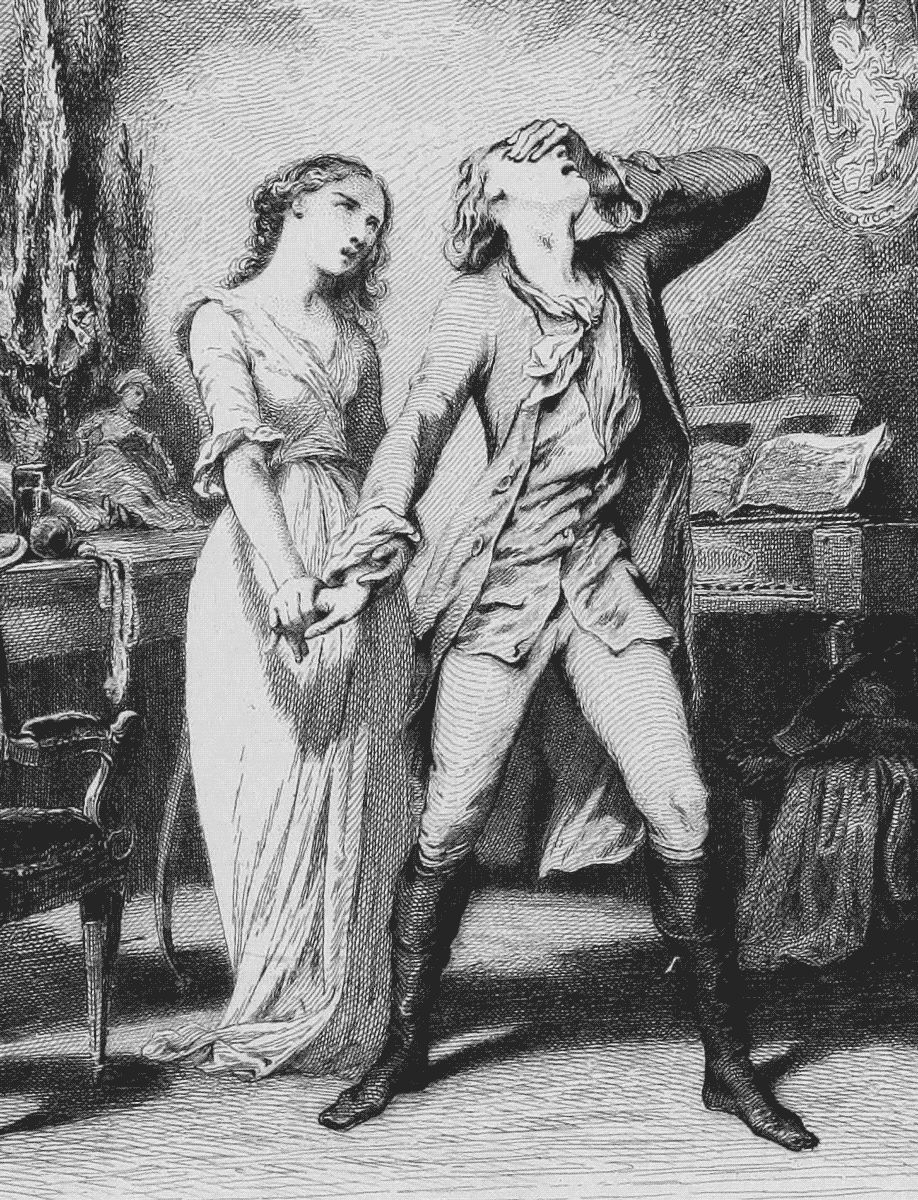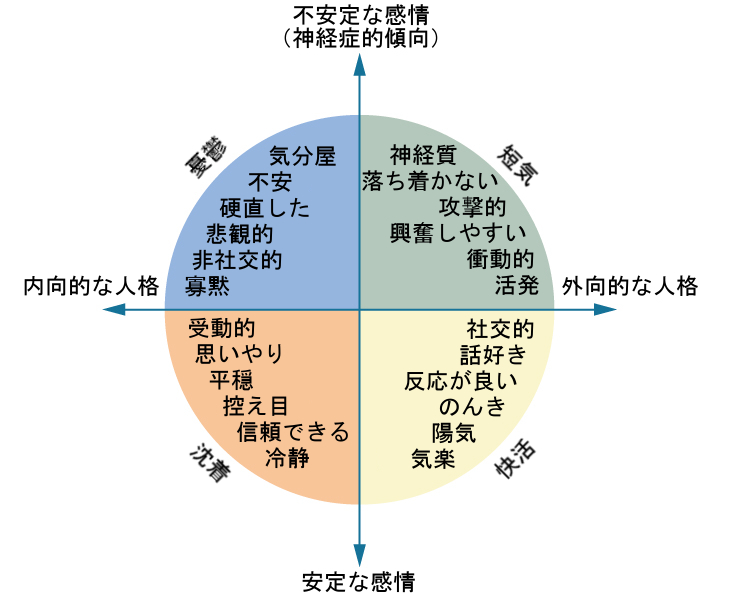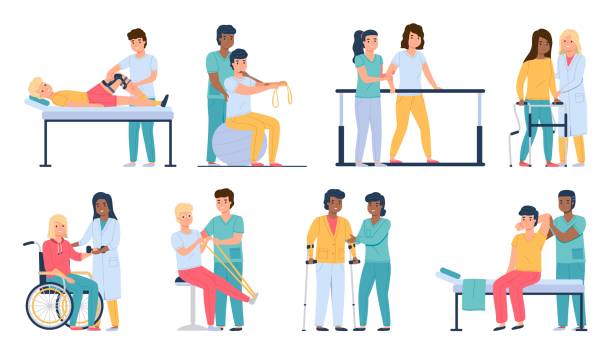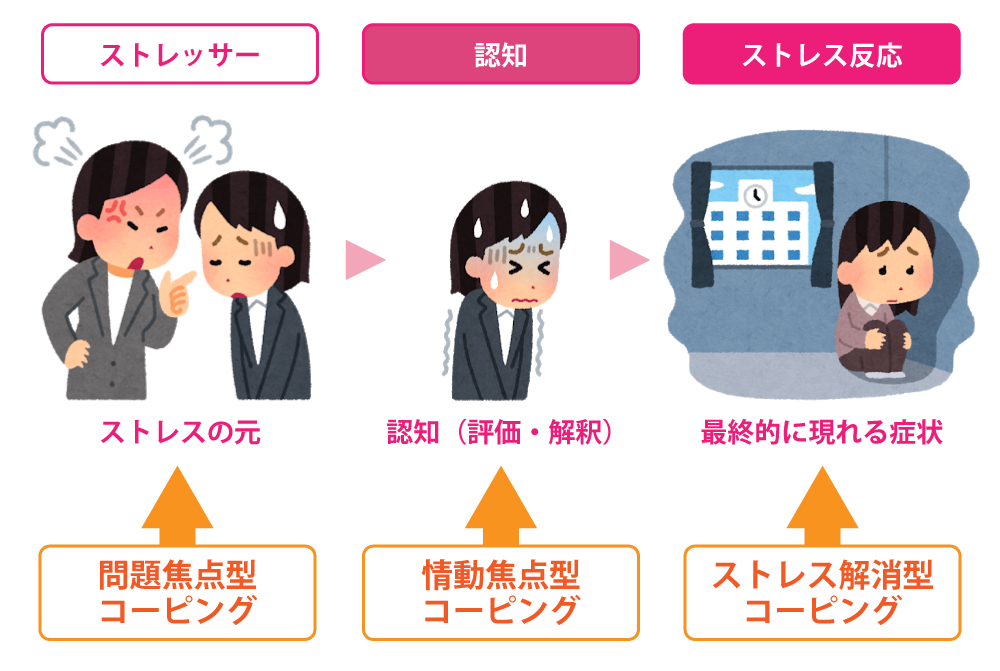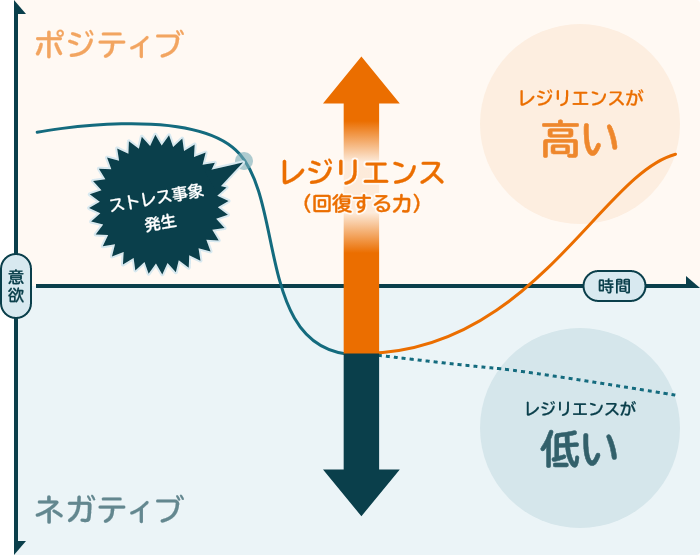2023年も残すところわずかとなりました。
ボクにとっては激動の一年間でありまして(笑)。この一年を通してボクは自分の進むべき道、進みたい道を模索しながら、歩んできました。
その一年を少しだけ振り返りたいと思います。
一月
まだ、前職の医療機関で働いていました。前月の十二月に「コロナ後遺症」と言うことで一ヶ月休職しており、新年とともに復職でした。昨年は一年を通じて、メンタル不調が原因で休職と復職を繰り返しており、正直、この復職にも、全く自信がありませんでした。
仕事は量・質ともに減らしていただいたのですが、それはありがたくもあり寂しくもあり。どんどん、仕事に対するやる気は失せていくのがわかりました。
そんな中、産業カウンセラーの筆記試験が下旬にあり、そちらの勉強も並行して行っていました。
二月
メンタル絶不調(笑)その頃はもう、職場にボクの居場所はなくて、話しかけてくれる同僚も殆どおらず、職場でのボクの評価は底をついたと思いました。そう認識したときから、この職場にはもう居たくないしボクは必要とされていないと思った瞬間から、一気にメンタルダウンしました。それがきっかけで中旬から休職しました。
三月
休職中に、元の職場に戻ることはボクにとっても同僚たちにとっても職場としても、なんの利点もない、と考え休職中に退職届を出し、前職を退職しました。ただ、現在のオンラインカウンセリングを個人事業主としてやっていこう、と言う思いは、二月に産業カウンセラーの筆記試験合格の通知を受け取っていたので、この頃からその構想が、現実に近づいていきました。
四月
とにかくお金がない!退職金もすぐ入らない、休職中の休職手当もすぐ入らない、しかも新型コロナに感染したことやその後の後遺症での休職が、労災扱いになるとのことで、手続きに時間がかかり、本当にお金がなかった。
ちょうど、失業保険の手続きのために訪れたハローワークにPSWさんの相談窓口があったため、すぐにそちらに相談したところ、名古屋市の公的機関二箇所を紹介してもらいました。
ひとつは障害者の就労や生活全般をサポートしてくれるところ、もう一つは障害者に限らず生活全般に困っている方への生活をサポートしてくれるところ。後者のサポートセンターでは、フードバンクサービスを利用させて頂き、2~3週間分の食料を頂きました。また、名古屋市の制度を紹介して頂き、3ヶ月分の家賃補助を受ける手続きもしました。
障害者就労支援センターでは、障害年金の相談や、ボクがやりたいと思っているオンラインカウンセリングの仕事へのアドバイス、副職へのアドバイスなどして頂きました。
五月
失業保険も給付され、また、滞っていた休職手当や労災金がもらえるようになり、少しずつ生活が立ち直っていきました。副業探しも本格的に始め、また、起業に関しても少しずつ自分なりに勉強を始めました。
また、前職中に在職中にボクは、多額の借金を作ってしまいました。それは双極性障害の影響もあり、金銭感覚が麻痺してしまっていたこともあります。そのため弁護士さんを紹介していただいて、「個人再生」の手続きを始めました。
この頃、ぷれいす東京のオンラインPGMを知ることができ、そこに参加することでボクは少しずつ自分の居場所を、見つけられるようになり、精神的にも安定してきました。
六月
副業は何社か受けたのですが全て不採用。不採用の連絡が来るたびに「自分の人格まで否定されているような感覚」に陥ることもあり、少し波もありました。また、ネットで起業するということで、愛知県が個人で起業する人向けへの相談事業を行っている場所へ行き、アドバイスを受けようとお話を聞いたのですが、ボクが過去に起こした不祥事がまだ尾を引きずっていることが分かり、酷く落ち込んでしまいました。
七月
ネット上に残っていたボクの「デジタルタトゥー」に対して対処し、改めてオンラインカウンセリングの事業について具体性を持って活動を始めました。本当は、副業が決まるまで待とうと思っていたのですが、副業が決まるのがいつになるのか、見通しが立たなかったため、先に自分の事業を開始しました。この「勇者の部屋」をプレ・オープンしたのもこの頃です。そして、ロゴの作成を依頼したり、プロフィール用写真撮影の段取りをしたり、というのがこの頃です。
そしてサイトも僕自身の手作りで全て始めました。
八月
オンラインカウンセリングをプレ・オープンし、五名の方と関わらせていただくことが出来ました。これはボクにとって、とてもとても大きな収穫であり、自信へと繋がりました。また、引き続き副職探しもしていたのですが、全く上手く行きませんでした。でも、自分がやりたいと心から思っていることが、何とかやって行けそうかも、と思ううちに、心も安定し、何事も前向きに取り組めるようになったのもこの頃です。
九月
満を持して「勇者の部屋」グランドオープンしました。ボクは心理職としての横のつながりを持っていませんでしたし、ビジネスとして成り立たせるための集客という概念が、ほとんどなく、もう勢いで始めてしまったところもあります(笑)しかし不思議と「何とかなる」と思っていました。その一つが、自分自信が過去にNGOの立ち上げや運営に携わった過去があり、なんとなくその経験が活かされそうだと思っていたからです。
並行して、JaNP+からのスピーカー派遣の依頼もあり、そちらのお仕事もさせてもらい、静岡まで講演のために足を運びました。数年ぶりのスピーカー活動であり珍しく緊張もしておりましたが「今回も引き受けて本当に良かった」と思える経験をさせて頂きました。
十月
グランドオープン後、有料サービスを開始し初めてのクライエントからの申込がありました。嬉しかったです。本当に。反面「心理カウンセリングをして対価を頂く」と言う事が初めての経験であったため、とても緊張もしましたし、何より、どなたのセッションでも自分への気付きが得られ、心豊かに成長していける、そんな感覚になっていました。
また、JaNP+のスピーカー派遣の依頼も受け、初めて厚生労働省という国の機関でお話をさせて頂くという、貴重な体験をさせて頂きました。いつも以上に緊張した覚えがありますが、とにかく本当によい経験になりました(後日、ご報告致します)。
十一月
プライベートでは、障害年金の申請を始めました。昨年九月に初回の申請をしたのですが、今回は、再申請するということで1年間待ち、社労士の先生のご指導のもと、精神科の主治医と連絡を取り合い、必要なサービスを利用しながら書類を作成していきました。
一方で、オンラインカウンセリングには、コンスタントにご利用して頂ける方がいてくださり、想定以上の経験をさせて頂きました。時には心悩ませることもあり、自分の力不足や不甲斐なさを感じることもありましたが、もっと経験を積んでもっと高みを目指したい!とも思える月でした。
また『RED RIBBON LIVE NAGOYA 2023』でHIV陽性者の当事者として登壇させて頂き、非常に短い時間でしたが、ボクの思いを伝えることが出来たと同時に、名古屋市の市の職員の方々と面識を持つことができた、貴重な機会となりました。
十二月
「パラちゃんねるカフェ」にてコラムライターとして出発しました。この一年、HIV陽性者であることを開示し活動を続ける中で、「偏見や差別は終わっていない」と肌身で感じる機会がたくさんあり、このコラムライターと言う仕事を通じて、HIV感染症だけでなく精神障害やセクシャルマイノリティと言う『マイノリティ要素』に対する偏見差別の解消に、ボクなりになにかできれば、ととても感じた1ヶ月でした。
それは『エイズ文化フォーラム in 名古屋 2023』に参加させて頂いた事も大きく影響しています。
もちろん引き続き、オンラインカウンセリングも行わせて頂き、クライエント様の問題が解決し終結を迎えても『勝水さんに定期的に話を聞いて欲しい』とご希望される方も何名かいらっしゃる事が、とてもありがたいし嬉しい思いでいます。
一方で『メンタル不調を抱えるゲイ・バイセクシャル男性のためのオンラインPGM』『メンタル不調を抱える対人援助職者・感情労働者のためのオンラインPGM』を企画し、始動し始めたところです。これは来年への課題として引き続き注力したいと思っています。
何事もそうですが『0から1にする力』というのは、非常に大変です。しかし幸か不幸かボクは『0から0.3くらいにする』ことから徐々に出力を上げて今は『0から0.6くらい』にやっとなってきたところかな~と思っていて、ある意味、無理のない範囲でやってこれました。来年は『0を1』にできるよう、残りの0.4をできるだけ早く埋めていきたいな~と、個人的には思っています。
ものすごく駆け足で2023年を振り返りましたが、ボクは要所要所で言葉にしてきました、「今のボクは皆さんの支援の元、成り立っています」と。本当に関わってくださった全ての方に感謝しかありません。どの方お一人欠けても今ボクは、ここに存在していなかったと思います。たくさんの『縁』で繋がりその繋がりが『線』になり活動を広げていくことで『面』へと発展し、もう少しで『立体』へと形作られる、一歩手前まで来ています。
今後、ボク自身が精進し、また皆様からのご支援を賜ることで『立体』が『多面体』になれたらとても素晴らしい何かが生まれると思っております。
今年一年、本当にありがとうございました。
ありがとう以上の感謝の言葉を皆様に贈りたいと思います。








.jpg/440px-Goethe_(Stieler_1828).jpg)