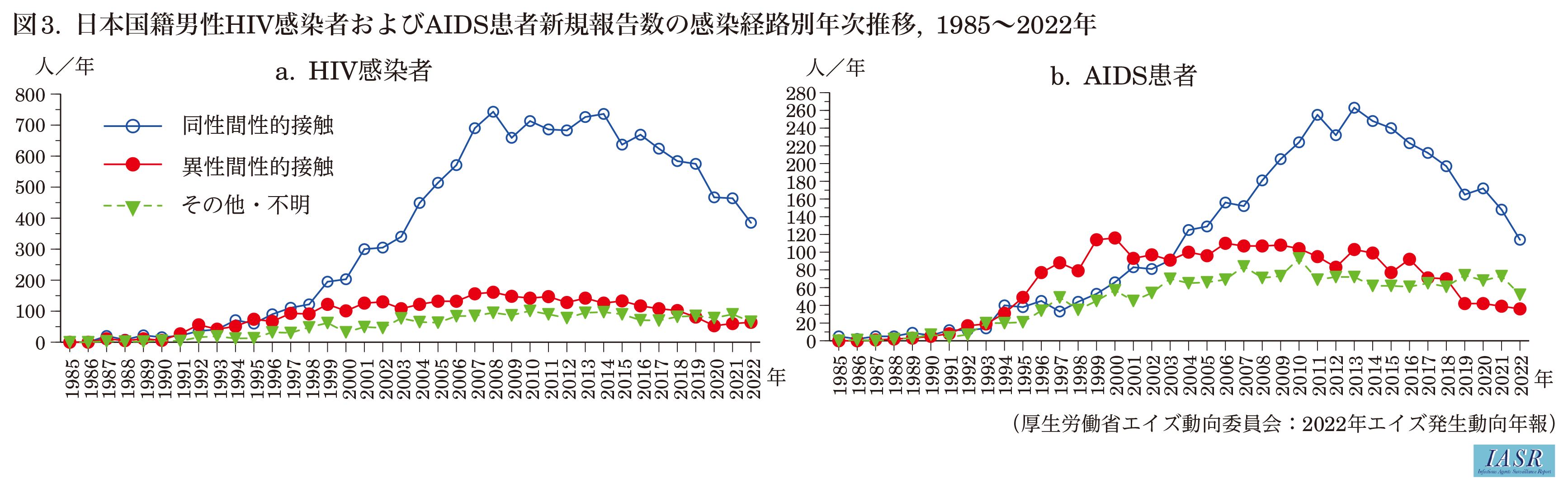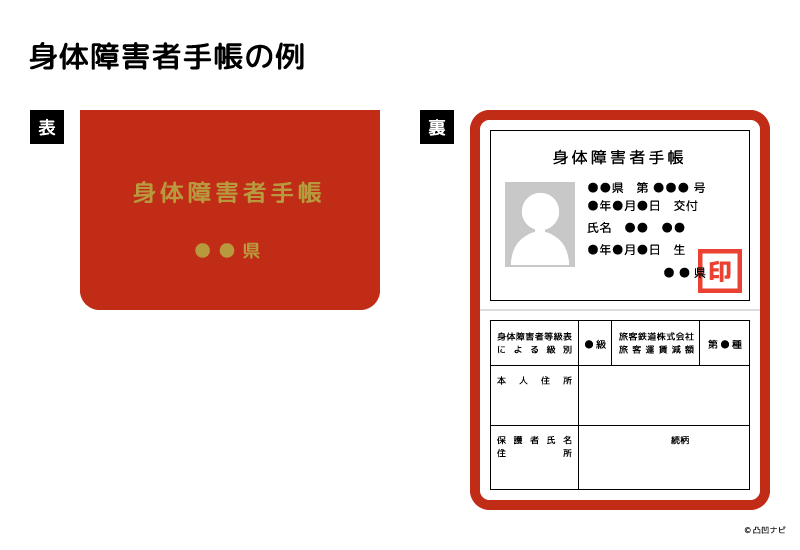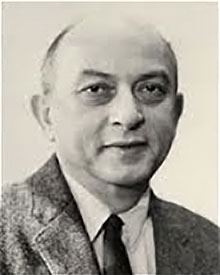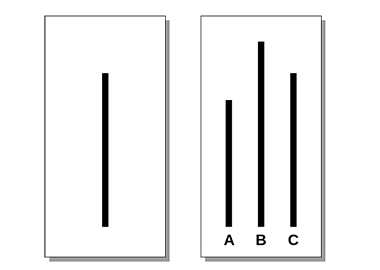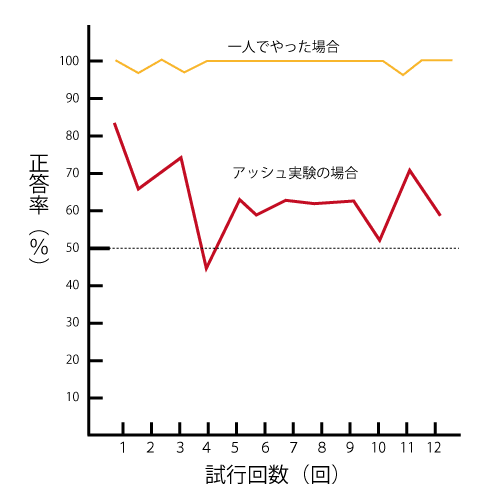実はこのところ、別々のクライエントさんから「愛憎」がテーマのエピソードをお聞きする機会が、何度かあったんです。ボクは、読書大好きっ子だったので(笑)「愛憎」という言葉は知っていましたし、「何となくこんなことだろうな~」と思っていたのですが、いい機会だと思い、深く調べてみました。
愛憎という言葉は「愛する心と憎しむ心」が複雑に絡み合った、人間の深淵を覗かせるような感情を表します。小説やドラマでは、愛憎劇がボクたちを惹きつけ、心を揺さぶります。そして、それはフィクションの世界だけの話ではありません。ボクたちの日常にも、愛憎は影を落とし、人生を大きく左右する力を持つことがあるのです。
1.愛憎の誕生:その背景にある心の葛藤
愛憎は、一体なぜ生まれるのでしょうか? その答えは単純ではないと思っています。それは人の心は複雑であり、愛憎の芽生えには、様々な要因が絡み合っているからです。
①失恋、離婚による心の傷
失恋や離婚は、深い心の傷をもたらします。 愛する人を失った悲しみ、裏切られた怒り、そして、自分自身の価値観さえも揺るがすような絶望感。これらの感情が渦巻く中で、かつて愛した相手への憎しみが芽生えることは、決して珍しいことではありません。
②自信のなさから生まれる不安
自分に自信がない人は、愛する人との関係においても、不安を抱きがちです。 愛情を失う恐怖、相手に捨てられるのではないかという不安、そして、自分自身の価値を認められない苦しみ。これらの感情が、愛する相手への過剰な束縛や、逆に突き放すような行動へと繋がる可能性があります。 これは、愛憎関係へと発展する土壌となります。
③他人に甘えてしまう依存的な性格
他人に依存しやすい人は、愛する人との関係においても、自分のアイデンティティや幸福を相手に委ねてしまう傾向があります。 相手の愛情が自分のすべてとなり、相手の言動に一喜一憂し、自分自身を見失ってしまう。このような状態は、相手への過剰な執着を生み、愛憎関係へと陥りやすくします。
2.愛憎関係:その特徴と危険性
愛憎関係は、以下のような特徴を持つ、不安定で破壊的な関係性だと言われています。
①感情のジェットコースター
愛情と憎しみが激しく揺れ動くため、関係は常に不安定で、感情の起伏が激しくなります。
②別れと復縁の繰り返し
関係が破綻しそうになると、愛情が再燃し、復縁を繰り返すパターンに陥ることがあります。しかし、根本的な問題は解決されないまま、再び同じような葛藤が生じ、関係は悪化していきます。
③衝動的な言動
感情に振り回され、冷静な判断ができなくなり、暴言や暴力、自傷行為、相手への嫌がらせといった衝動的な行動に走ってしまうことがあります。
④執着と依存
相手への執着が強くなり、相手の行動を監視したり、束縛しようとしたりします。また、相手に依存し、自分自身を見失ってしまうこともあります。
⑤コミュニケーションの破綻
感情的な対立が激化し、冷静に話し合うことができなくなります。互いの気持ちを理解しようとせず、非難や攻撃ばかりを繰り返すようになり、関係はさらに悪化していきます。
愛憎関係は、深刻な事態を招く可能性も孕んでいます。 感情の激化は、暴言や暴力、自傷行為、さらには心中や殺人といった取り返しのつかない悲劇に発展することもあります。 また、愛憎関係は、当事者双方に深い心の傷を残し、その後の人生にも大きな影を落とす可能性があります。
3.愛憎の克服:そのための具体的なステップ
愛憎の感情に苦しんでいる場合、どのようにすれば、その苦しみから解放され、健全な関係を築くことができるのでしょうか? 以下に、具体的なステップの一例をご紹介します。
①関係からの距離
まずは、愛憎の対象となっている相手や状況から、物理的にも精神的にも距離を置くことです。 これは、感情の波を鎮め、冷静さを取り戻すために必要なステップです。
②自己理解
自分自身の感情と向き合い、なぜ愛憎を抱いているのか、その原因を探りましょう。 幼少期のトラウマ、過去の恋愛経験、自信のなさ、依存的な性格など、様々な要因が考えられます。
③コミュニケーション
相手との関係を見直し、率直に気持ちを伝え、お互いのニーズを尊重したコミュニケーションを心がけてみてください。
④境界線の設定
自分と相手の境界線を明確にし、過度な干渉や依存を避ける必要もあるのでは?
⑤自己受容
自分の感情や弱さを認め、ありのままの自分を受け入れて。 完璧主義を捨て、自分を許すことで、心の安定を取り戻すことができます。ただ、これは難しい(汗)愛憎関係にある時、当事者はお互いに、「相手に原因がある」と思い込んでいることも多いんですよね…だから、自分をありのままに受け入れるって、かなりしんどいと思います。
⑥専門家のサポート
自分一人で解決できない場合は、心理カウンセラーやセラピストなどの専門家の助けを求めましょう。 専門家のサポートは、愛憎の根本的な原因を理解し、克服するための具体的な方法を学ぶ上で、大きな助けとなります。
4.愛憎の深淵に光を:未来への希望
愛憎は、確かに複雑で苦しい感情です。しかし、克服できる可能性は十分にあります。自分自身の感情と向き合い、適切な対処法を実践することで、愛憎の苦しみから解放され、健全な人間関係を築き、より豊かな人生を送ることができると思っています。
ボク、よく事あるごとに投げかける質問で「愛情の対義語は?」とお聞きします。もちろん諸説あるのですが、その中に「無関心」という言葉があります。
「愛情」の対義語は「憎しみ」ではない、とボクは理解しています。
つまり、憎しみというのは、『対象となる相手に関心を寄せている』とも言う点で「愛情」と近しい感情である、とボクは思っています。
「愛憎」の感情というのは、時として、長く引きずることがあります。それは、愛憎の対象となる人と物理的に距離が離れたり、他界したりといったことで、その対象に直接的な感情をぶつけることが困難になった時です。
すると人はどんどん、愛憎が鬱積し知らぬ間に生活に入り込み、新しい人との人間関係にまで影響を及ぼすことも…
憎しみをぶつけたい…でもその相手はもう手の届かないところに…このジレンマに陥ると非常に苦しいと思います。
やっぱり、そんな時、絶対なる第三者である心理カウンセラーを利用することをオススメします。









.jpg)
.jpg)